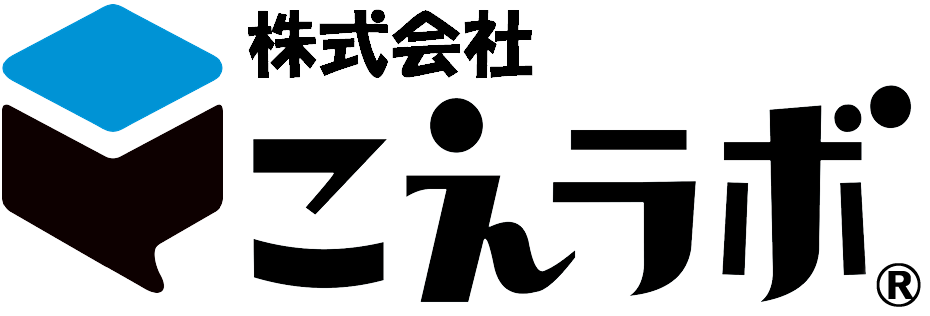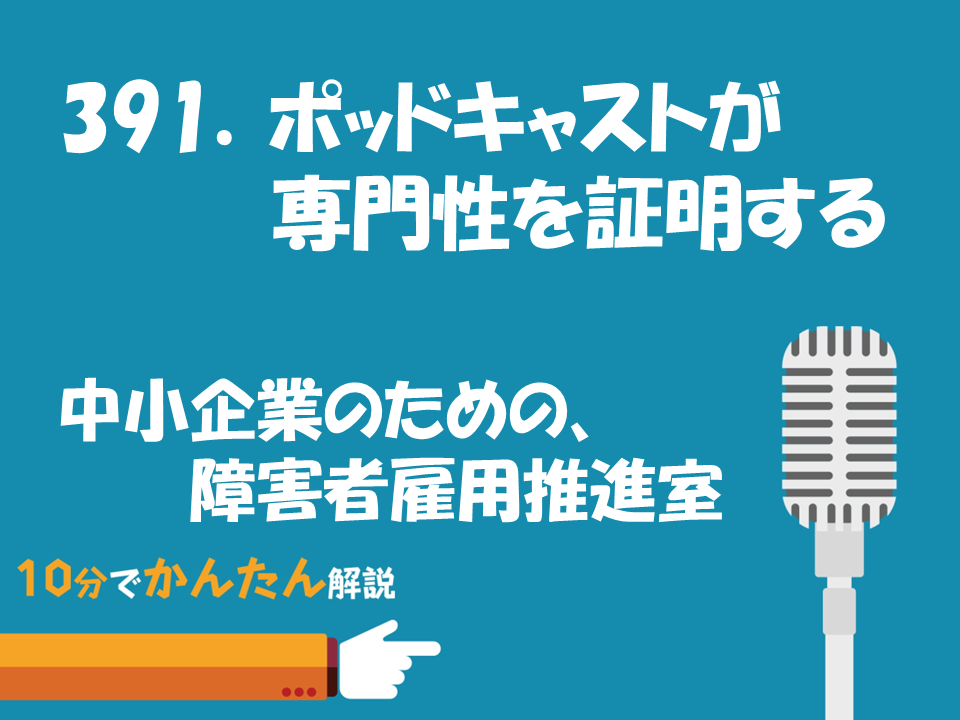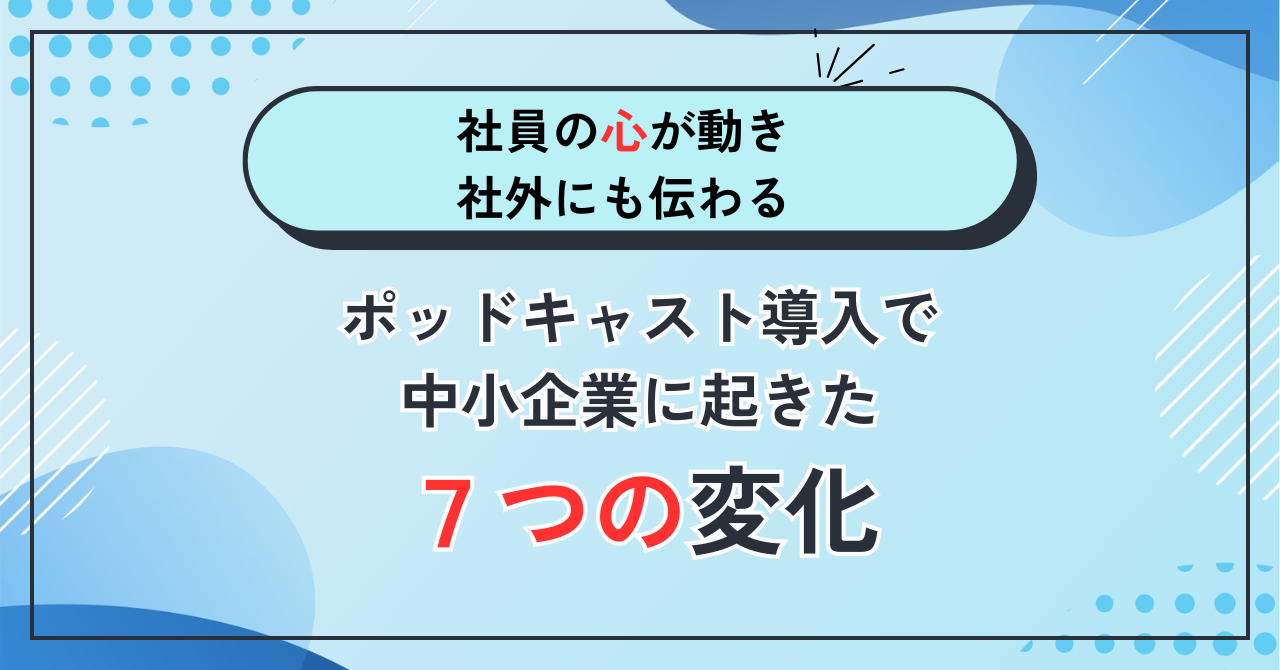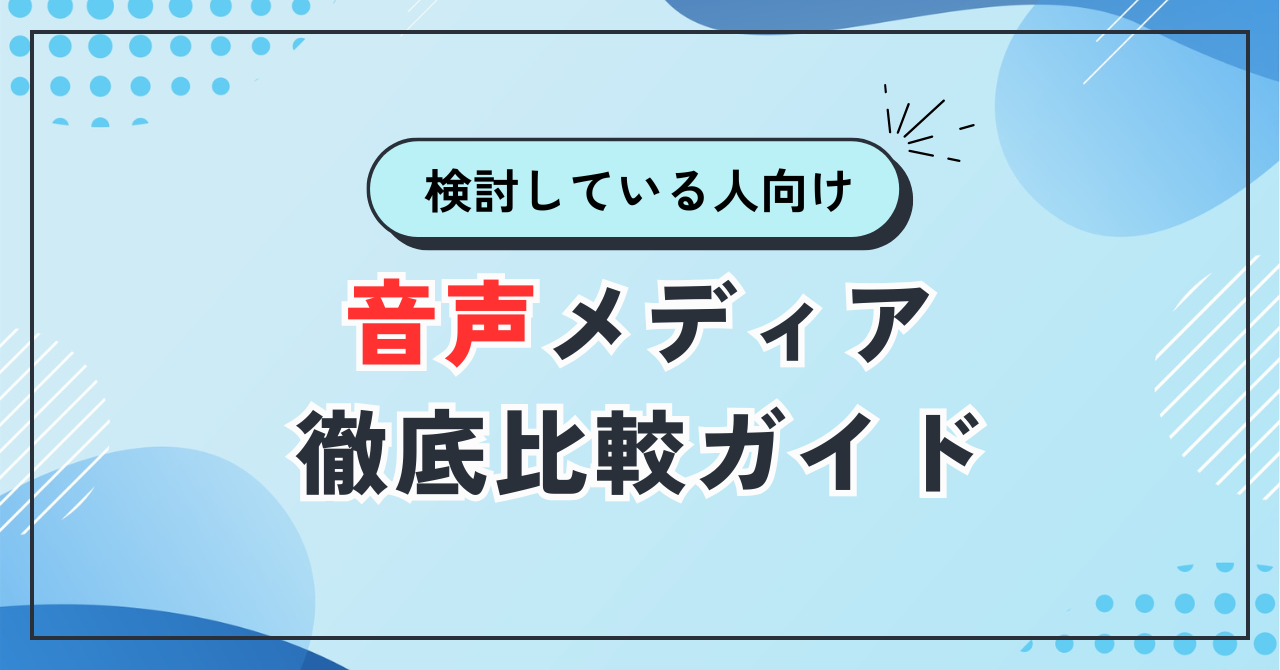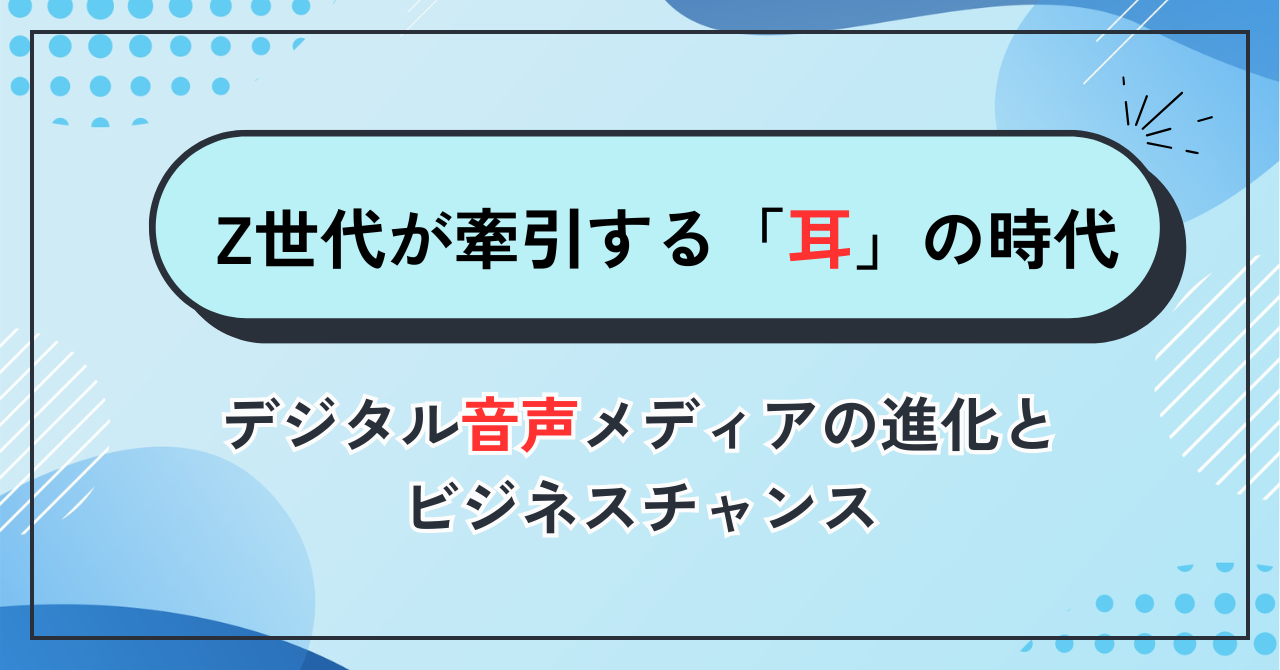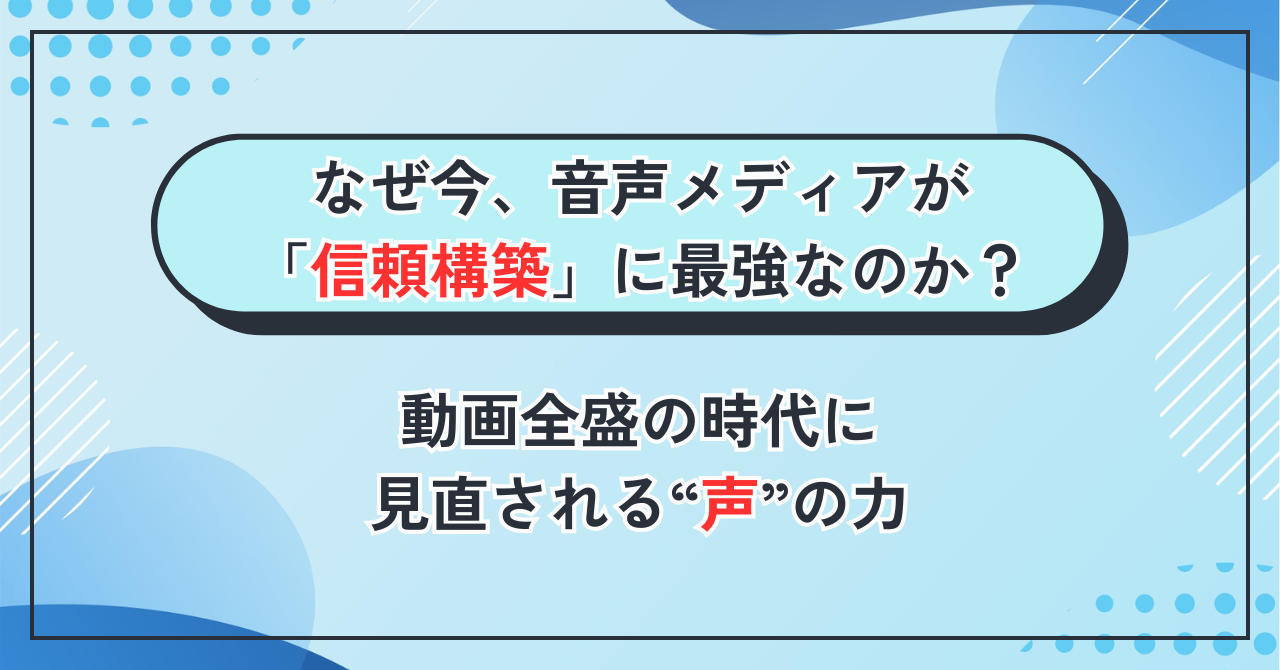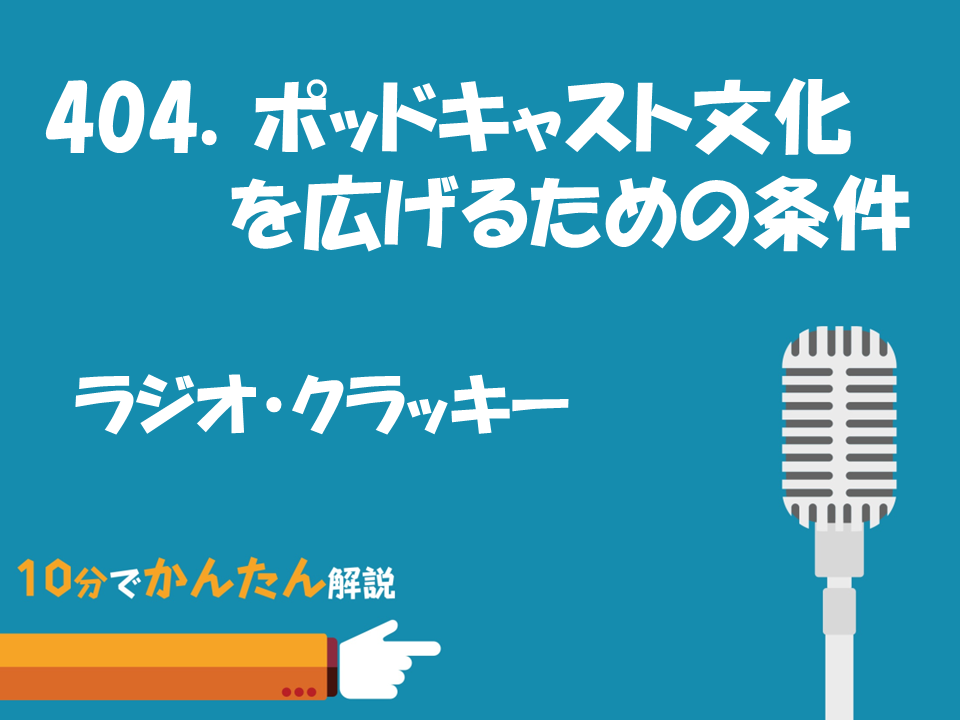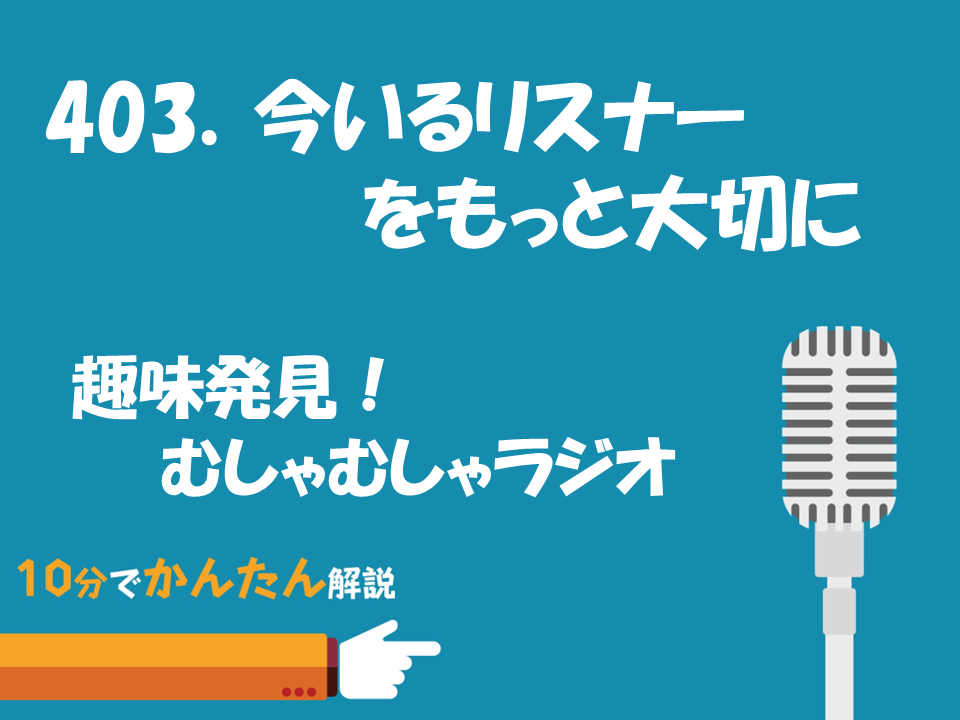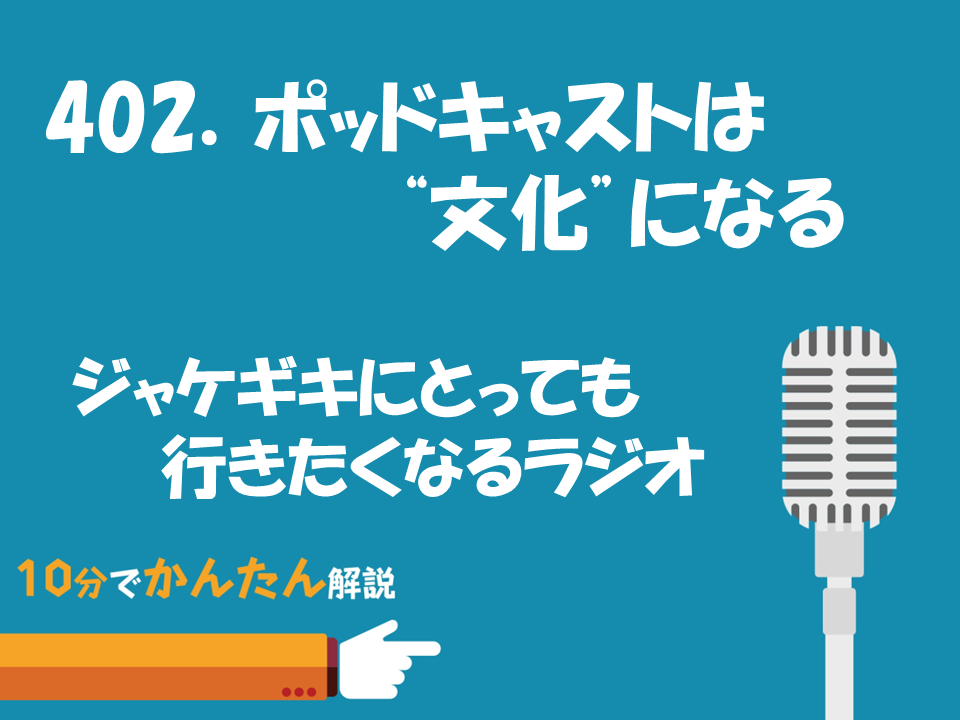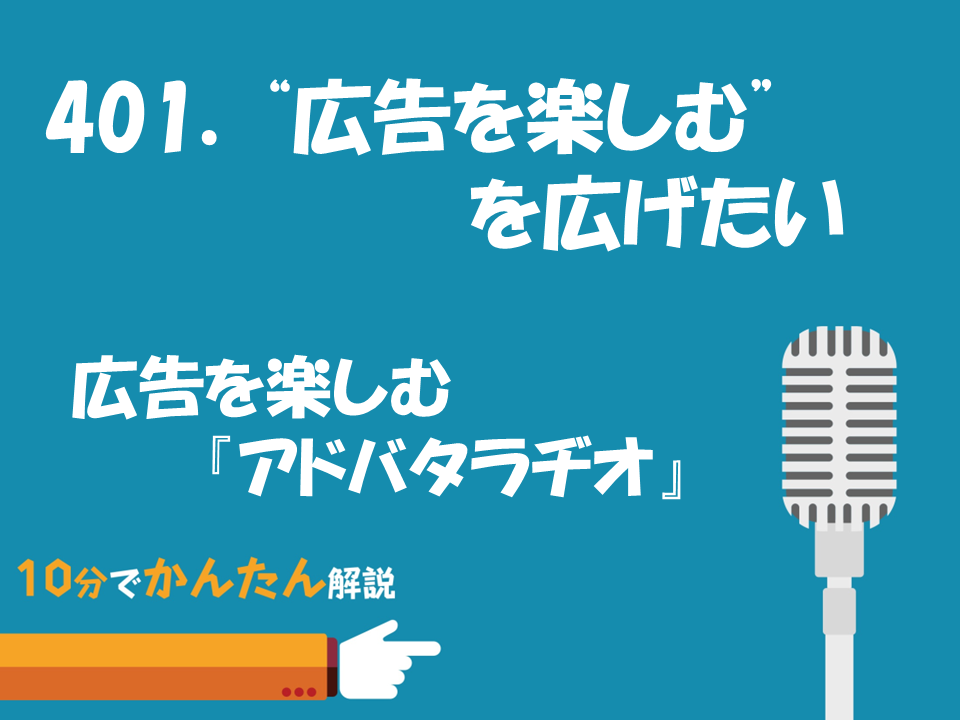ポッドキャストステーション
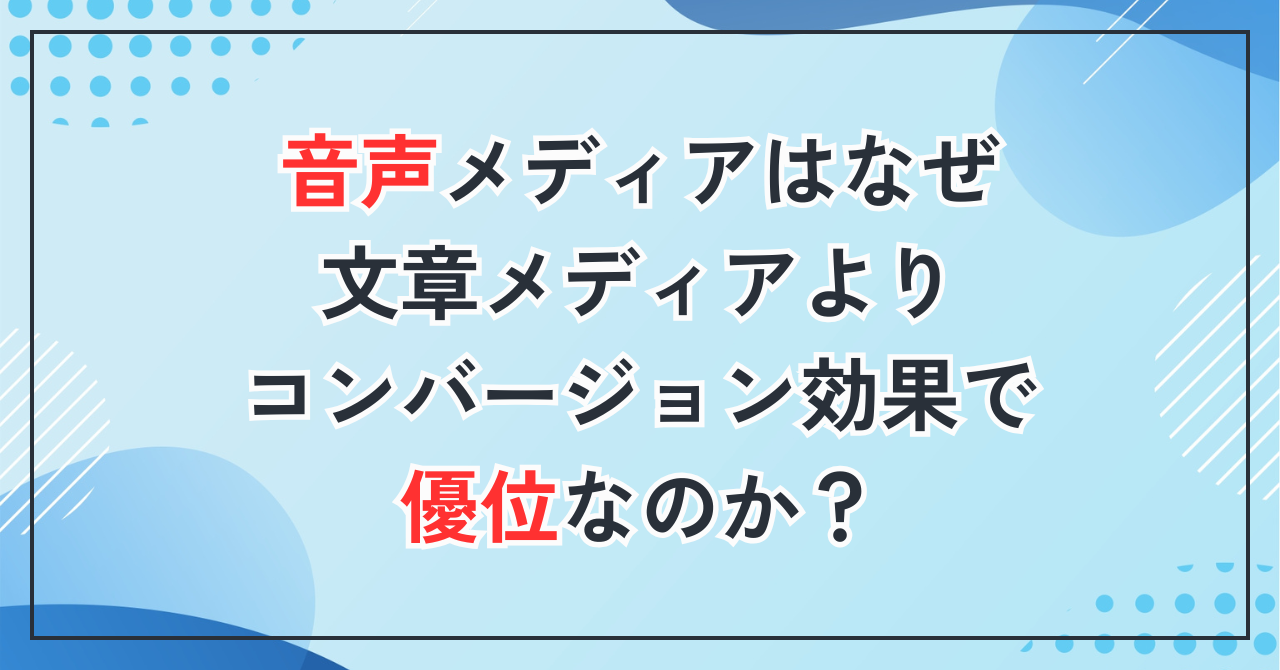
音声メディアはなぜ文章メディアよりコンバージョン効果で優位なのか?
企業のマーケティング手法として、テキスト中心のブログやメルマガ、SNS投稿などの「文章メディア」と、ポッドキャストや音声配信、デジタルラジオといった「音声メディア」の二つがあります。本記事では信頼できるデータ(2020年以降の政府・業界調査や学術研究等)をもとに、両者を比較しながら、特に「コンバージョン効果」(問い合わせや商品購入などの成果)において音声メディアが優れている根拠を解説します。さらに、音声メディアがもたらす信頼性・親密性、コンテンツ消費時間・継続率、ブランディング・ファン化、記憶や感情への影響といった観点も掘り下げます。
ターゲット読者である事業拡大志向の経営者の皆様にとって、音声メディア活用の有用性が論理的かつ読みやすく伝わるよう努めます。
音声メディア利用の拡大と市場の変化
まず背景として、日本における音声メディア市場は近年急速に拡大しています。総務省や電通の調査によれば、ラジオ広告費は2021年以降増加傾向に転じ、2021年から3年連続で前年を上回りました。これはインターネット経由のラジオ聴取(radiko等)の普及によるリスナー増加が一因と分析されています。また、デジタル音声広告市場も年間2ケタ成長で拡大すると予測されており、ポッドキャスト利用率も2024年時点で17.2%(約1,840万人)に達するなど着実に浸透しています。
Z世代を中心に「耳で情報を得る」文化が広がり、「ながら聴き」のしやすさや生活への取り込みやすさから音声メディアの定着が進んでいます。例えば18~34歳の若年層では通勤・通学中、家事中、就寝前など様々なシーンで音声コンテンツが利用されており、コロナ禍以降その傾向が一段と高まっています。こうしたユーザー行動の変化が、市場拡大と企業の音声活用への注目を後押ししています。
コンバージョン効果で音声メディアが優位な根拠
音声コンテンツは購買行動に直結しやすい
最大の論点であるコンバージョン効果について、まず定量データを見てみましょう。朝日新聞社と音声マーケ企業オトナルが共同実施した国内調査(2021年)によれば、ポッドキャストを聴いた情報を「実際に検索したことがある」人は57.9%、さらに「実際に商品購入したことがある」人も29.9%にのぼりました。つまり音声コンテンツをきっかけに約3割のユーザーが商品購入等の行動を経験しているわけです。この数値は、一般的なウェブ広告のクリック率やテキスト記事からの直接購買率と比較しても非常に高い水準といえます。
さらに若年層ではその傾向が顕著です。ある調査ではZ世代のポッドキャストユーザーのうち64.4%が聴取後に検索を行い、40.6%が商品・サービスを購入した経験があると報告されています。特筆すべきは、朝日新聞の公式ポッドキャスト番組の聴取者に限れば82.9%が検索し、実に65.2%が購入に至ったというデータです。情報感度の高い層では音声メディア経由でのコンバージョン率が半数を超える例すらあるのです。
音声広告キャンペーンの実績
具体的な企業事例として、三井住友カード社がSpotify上で展開した音声広告キャンペーンの成果を見てみましょう。同社は新クレジットカード告知のために16パターンもの音声クリエイティブを配信し効果測定を行いました。その結果、直接の即時コンバージョン(その場での申込)は多くなかったものの、後日の間接コンバージョンが200件以上計測されました。これはユーザーが音声広告を聴いた後で検索やサイト訪問を経由して申し込んだ件数で、音声広告が時間差で確かな成果に結びついていることを示しています。
加えて、同キャンペーンでは広告認知率(広告を認識・想起できた人の割合)が70%以上に達したと報告されています。通常、テレビCMなどマス広告の認知率は30%程度に留まるケースが多い中、音声広告では圧倒的に高い想起率が得られたことになります。担当者は「他媒体と比較しても音声広告は有効だと実感した」と述べており、検索数の押上げ(サーチリフト)や高い広告想起率などマルチな指標でポジティブな効果が確認できたとしています。
以上のように、信頼性の高い調査データや実企業のケーススタディから、音声メディアは文章メディアに比べてユーザーの購買行動を喚起しやすいことが伺えます。では、なぜ音声はこれほどコンバージョンにつながりやすいのか? 次章以降でその理由を4つの観点から考察します。
信頼性・親密性:声が生む強いパーソナルな繋がり
文章による情報発信と比べ、音声は圧倒的に「人柄」や「温度感」が伝わりやすいメディアです。人は声色や話し方から発信者の感情や誠実さを感じ取るため、音声コンテンツではリスナーとの心理的距離が近づき、信頼関係や親近感が醸成されやすいとされています。例えば、電通と脳科学者による実験的考察では「ラジオは話し手がまるで耳元で語りかけてくれるような感覚を与え、リスナー一人ひとりがパーソナリティとの関係を築いている」と分析されています。その結果、「パーソナリティが話すと、多少高価なものでも『買おうかな』と思うリスナーがいる」とも言及されました。これは声による訴求が生身の人間から直接おすすめされているように感じられるため、商品やサービスへのハードルが下がるからでしょう。
実際、米国市場の事例ですが人気ポッドキャストではホスト(配信者)と聴取者の強い信頼関係が築かれており、ホストがおすすめする商品はリスナーから受け入れられやすいことが知られています。日本においても同様の傾向が見られ、音声広告が「押し付けがましくない形」で生活者に届くため警戒感が低いことが指摘されています。文字の広告ではスルーされがちな宣伝情報でも、音声なら耳を傾けてもらいやすく潜在意識に残りやすいのです。また音声メディアは広告臭さが前面に出にくいため、「ガードを下ろした状態」でメッセージを届けられるメリットもあります。
さらに、ラジオ業界では以前から「音声は想像力を掻き立て、信頼を醸成し、ブランドへの好感度を高めファン化を促すメディアだ」という通説がありました。2023年のradikoの発表によれば、これらは単なる感覚論に留まらず脳科学実験でも裏付けられ始めています。声だけで情報を伝えるメディアだからこそ、「この人の話をもっと聞きたい」「この人がおすすめするなら信じてみよう」という深いエンゲージメント(心の繋がり)が生まれやすいと言えるでしょう。
コンテンツ消費時間・継続率:長く深く届けられる音声
音声メディアの強みの二つ目は、ユーザーに長時間コンテンツを消費させ、継続利用してもらいやすい点です。文章コンテンツはどうしても読むのに視線と時間を独占してしまうため、忙しい現代人にとって腰を据えて読むにはハードルがあります。一方、音声コンテンツは「ながら聴き」が可能なので、通勤中や運動中、家事の合間など日常のスキマ時間を有効活用してもらえる利点があります。事実、ポッドキャストの1エピソードは30分~1時間程度の長さが一般的ですが、車移動やジョギングといったまとまった時間を充てやすいシーンで消費されるためリスナーのエンゲージメントが高いことが報告されています。
また、音声は目や脳に対する疲労感が少ないメディアでもあります。動画視聴や長文読解は情報量が多く集中力を要するため「疲れる」と感じる人もいますが、音声なら耳から情報を得るだけなので映像ほど疲れないというユーザーの声があります。実際「動画より音声の方が疲れずに情報収集できる」と感じる女性Z世代は45%にも上り、他世代より10ポイント以上高いという調査結果もあります。このようにストレスフリーに長時間接触できる点で、音声は現代の情報過多社会にマッチしたメディアと言えるでしょう。
継続率(リテンション)の高さも見逃せません。興味深いことに、ポッドキャストは一度聴き始めたら最後まで聴かれる割合が高いとされます。倍速再生や一時停止を挟みつつでもユーザーは番組を習慣的に消化し、次回エピソードを待ち望む傾向があります。これは文章メディアで記事を途中離脱されてしまうケースと対照的です。さらに、音声プラットフォーム側の仕組みとしてSpotifyやradikoの音声広告はスキップ不可となっており、配信した広告メッセージが確実に耳に届く仕様であることも広告接触率を高める一因です。
要するに、音声メディアはユーザーの生活時間に溶け込みやすく、結果としてコンテンツ消費量や継続利用を伸ばせるため、マーケティング上も深い訴求や複数回接触による関係構築が期待できるのです。
ブランディング・ファン化:声によるブランド体験の深化
ブランド構築の観点でも、音声メディアはテキスト以上に効果的な場面があります。前述の通り音声は人間味や温度感を伝えやすいため、ブランドのメッセージや世界観をユーザーに親身に感じ取ってもらえるのです。例えばSpotifyが実施した調査では、音声のみの広告は他の広告媒体に比べてブランド認知度を高める効果が高かったと報告されています。映像やバナーと異なり音声広告はユーザーの注意を一点に引き付けやすく、「このブランドの声が聞こえてくる」という体験を通じて記憶に残るブランド印象を形成できるのでしょう。
音声コンテンツではしばしばパーソナリティ(話し手)=ブランドの分身となります。企業の公式ポッドキャストで社員や経営者自らが声を届けるケースも増えていますが、聴取者にとってはその声を通じてブランドの価値観やストーリーに直接触れる体験となります。ラジオ業界で昔から「音声は商品・ブランドへの好感度を高め、ファン化を促進する」と語られてきたのはまさにこの点です。音声はイメージ映像のような視覚要素を伴わないぶんリスナー自身の想像力でブランド像を補完させ、より能動的・情緒的にブランドと関わってもらえる効果があります。
さらに、音声メディアの特徴として双方向的な関係構築も挙げられます。たとえば音声SNSやクラブハウス的なライブ配信ではリスナーのリアクションを拾ったり、ポッドキャストでもお便り紹介やSNSでの感想共有を通じてコミュニティ感が醸成されます。文章メディアにもコメント欄などはありますが、声で直接コミュニケーションする親密度には及びません。「絆メディア」とも称される音声プラットフォームにおいて、一度ブランドの世界観に共感したリスナーは強力なファン・支持者となりやすく、そのエンゲージメントはやがてLTV(顧客生涯価値)の向上にもつながっていくでしょう。
情報の記憶・感情への影響:脳科学が示す音声の力
最後に、記憶定着率と感情喚起の面から音声メディアの優位性を見てみます。文章を読んだ情報より、人の話し声で聞いた情報のほうが印象に残りやすい――感覚的にそう思われる方も多いでしょうが、近年これは脳科学実験でも実証されています。2023年にradikoが発表した研究によれば、音声広告は映像広告に比べて「商品・サービス名」や「広告ストーリー」の記憶率・記憶維持率が高いことが確認されました。実験参加者に実際のテレビCMとラジオCMを視聴させて比較したところ、1週間後の追跡テストで音声CMを聞いた人の方が商品名を覚えている割合が有意に高かったのです。また生理指標の計測から、音声広告の聴取中は交感神経が優位になり注意が向上した状態になることもわかりました。専門家は「音声メディアは聴き手の脳内で情報を自分ごと化(自分に関係ある情報として捉えること)させ、記憶形成を助ける働きがある」とコメントしています。
アンケート調査の結果もこれを裏付けます。別途行われた意識調査では「音声を聞いたときの方が、過去の出来事や触れた状況を思い出しやすい」、すなわち音声は記憶想起を促し「自分ごと」として捉えやすいとの回答が多数を占めました。実際、朝日新聞社の調査でも音声広告を聴いたユーザーの31.6%が「商品・サービス名が記憶に残りやすい」と感じているという結果が出ています。これは聴覚情報の方が五感の中でも想像力を掻き立て、脳内でイメージ補完されるためだと考えられます。「音を聞くと以前の記憶や体験が甦る」というのは誰しも経験があるでしょうが、その特性が広告メッセージの想起率向上にも寄与しているわけです。
また、感情への働きかけも音声ならではの強みです。電通サイエンスジャムの研究によれば、感情を伴う体験は記憶に残りやすいとされますが、音声メディアはまさにリスナーの感情にダイレクトに訴求できます。声のトーンや抑揚、BGMや効果音によって喜怒哀楽やワクワク感を伝染させる力はテキストよりはるかに大きいでしょう。前述の電通の実験では「ラジオは話し手と聞き手の心理的距離が近いため、そこで生まれる感情も特別なものになる」と分析され、音声によってリスナーの心が動かされ購買意欲につながるケースも確認されました。声に乗せられたメッセージは感情というエンジンで記憶に深く刻まれ、行動を駆動する──これが音声メディアの持つ底力なのです。
まとめ:事業拡大に音声メディア活用を
以上、音声メディアと文章メディアを多面的に比較し、特にコンバージョン効果において音声が優位である理由をデータとともに見てきました。音声メディアは利用者の購買行動を直接・間接に後押しし、高いコンバージョン率を実現できる可能性があります。それを支える背景には、声が生む圧倒的な信頼感・親密性、生活の中で長時間接触してもらえる利便性、ブランドメッセージを深く刻みファンを生む力、そして記憶と感情に訴えかける影響力が存在します。テキスト情報だけでは成し得ないレベルで顧客との関係性を構築できる点で、音声メディアはマーケティングチャネルとして独自の価値を発揮します。
事業がある程度成功しさらに成長を狙う経営者の方々にとって、次の一手として音声メディアを取り入れる戦略は十分検討に値します。例えば自社のポッドキャスト番組を立ち上げて製品やサービスの魅力を語ったり、人気音声プラットフォーム上でターゲット層に絞った音声広告を配信することで、新たなリード獲得や顧客エンゲージメント向上が期待できるでしょう。実際、日本でも音声マーケティングに乗り出す企業は増えており、その成果が少しずつ可視化されつつあります。
競合他社に先駆けて「耳の市場」にリーチし、声ならではのブランド体験でユーザーの心をつかむことができれば、ビジネス拡大の大きな原動力になるに違いありません。興味を持たれた方は、ぜひ専門サービスの提供する資料や事例集をご覧になり、音声メディア活用の具体像を掴んでみてください。詳しい情報や導入支援についてはこえラボの資料請求もご活用ください。